横浜住宅建築相談所は、欠陥住宅・住宅・建築トラブル等を予防するための建築請負契約締結等の住宅・建築・法律トラブル相談を横浜市を中心に相談実施中。
TEL. 0120-375-530
相談予約専用 録音による24時間相談電話受付中
建築工事請負契約のポイントHEADLINE
建築工事請負契約のトラブル
建築工事請負契約の締結時のトラブルについて考えてみましょう。
土地等の不動産を購入して建物を建築する際に建築施工業者と交わすのが「建築工事請負契約書」になります。
この建築工事請負契約書にトラブルが多く発生しています。
なぜ?このようなトラブルが多く発生するのか?
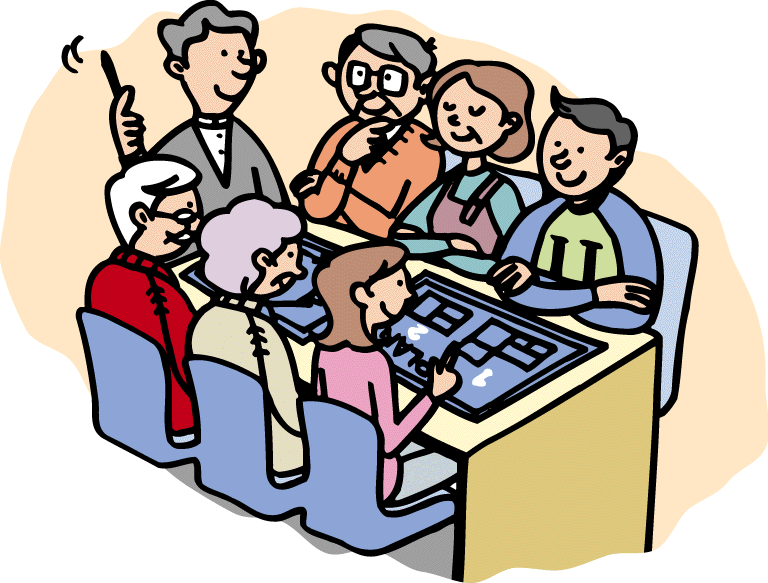
請負契約に係るトラブルの要因を見てみましょう。
と請負契約締結において多く見られるトラブル事例としては・・・
①請負契約で締結した内容と違う家ができている。
②請負契約を先行して締結したが、建築物の内容・予算が大きく変わってきたので解約したい。
③請負契約で約束した建築工事期間を過ぎて建物が完成したが、請負金額通りの請求をされている。
大きくこれらの事例が相談として寄せられるています。
土地等の不動産を購入して建物を建築する際に建築施工業者と交わすのが「建築工事請負契約書」になります。
この建築工事請負契約書にトラブルが多く発生しています。
なぜ?このようなトラブルが多く発生するのか?
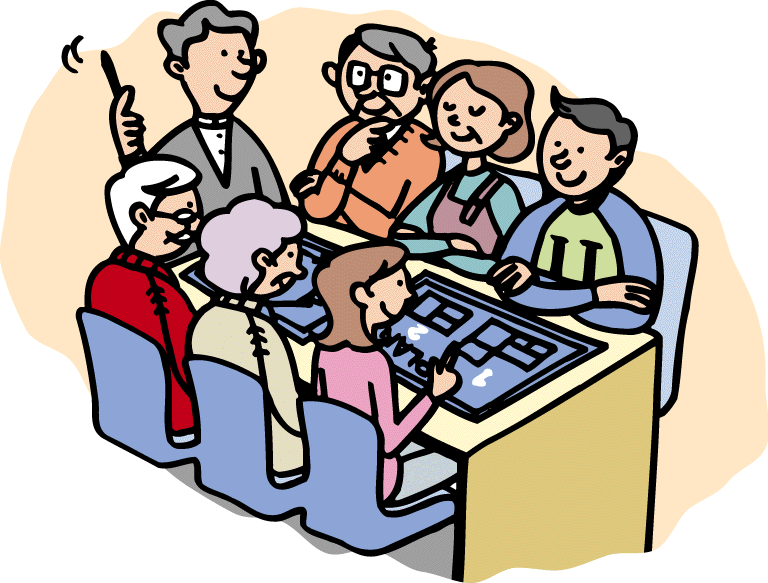
請負契約に係るトラブルの要因を見てみましょう。
と請負契約締結において多く見られるトラブル事例としては・・・
①請負契約で締結した内容と違う家ができている。
②請負契約を先行して締結したが、建築物の内容・予算が大きく変わってきたので解約したい。
③請負契約で約束した建築工事期間を過ぎて建物が完成したが、請負金額通りの請求をされている。
大きくこれらの事例が相談として寄せられるています。
しっかりした請負契約を締結するポイント
一般的に、建築工事を施工業者やハウスメーカーに依頼する際に、建築工事請負契約書を締結しますが、しっかりとした請負契約を締結するためのポイントを考えてみましょう。
もっとも、わかりやすく考えるなら、「どのような家を、いくらで、何時までに建ててもらうのか?」
この言葉が、しっかりとした請負契約を締結するための基本となってきます。
もっとも、わかりやすく考えるなら、「どのような家を、いくらで、何時までに建ててもらうのか?」
この言葉が、しっかりとした請負契約を締結するための基本となってきます。
請負契約は口頭でも成立する
契約は法律的には「口頭」でも成立します。つまり、「家を建てたい」「建てましょう」と言った会話だけでも請負契約は有効に成立します。
ただ、この口約束だけでは、「どんな建物を?」「いくらで?」と言った肝心の内容は一切確認されていませんが、これだけでも契約は成立するのだということを理解していれば、次のような請負工事のトラブルを回避することができます。
よくある場面です。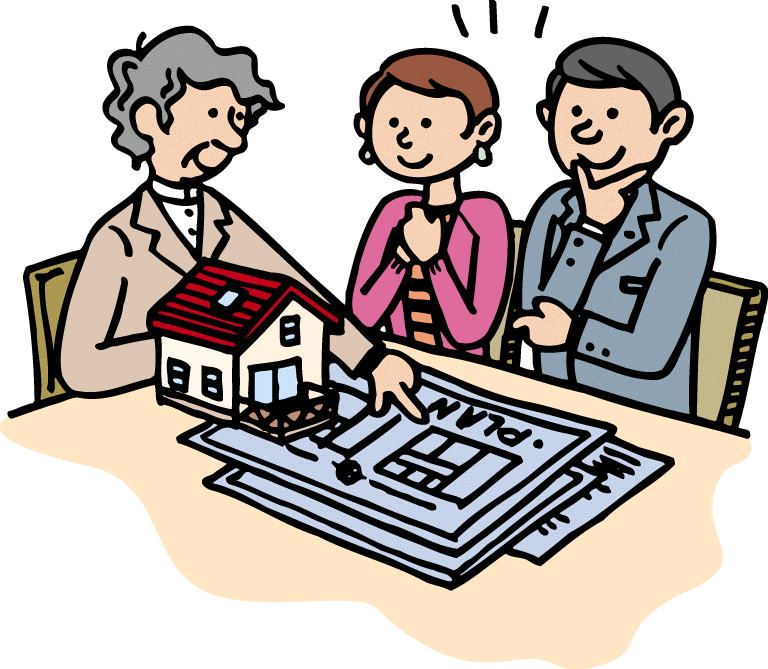
建築条件付き土地売買契約のケースなどでは、土地の売買契約締結後、直ちに建物の建築請負契約を締結するケースがあります。この段階では、何も「家の内容」が決まっていなくても、請負契約書に印鑑を押してしまいがちです。
口頭だけでも請負契約が成立するのですから、間違いなくこのような状況では請負契約は成立します。
例え、「何も決まってなくとも」
大事なのは、図面や仕様書を作成し、「どのような家」を建てるのか?
その図面や仕様書を基に、見積書を作成し建築費用がいくらかかるのか?工事金額を明らかにしたうえで、注文者・施工者であるあなたと施工業者が「請負契約」を成立させることが重要です。
ただ、この口約束だけでは、「どんな建物を?」「いくらで?」と言った肝心の内容は一切確認されていませんが、これだけでも契約は成立するのだということを理解していれば、次のような請負工事のトラブルを回避することができます。
よくある場面です。
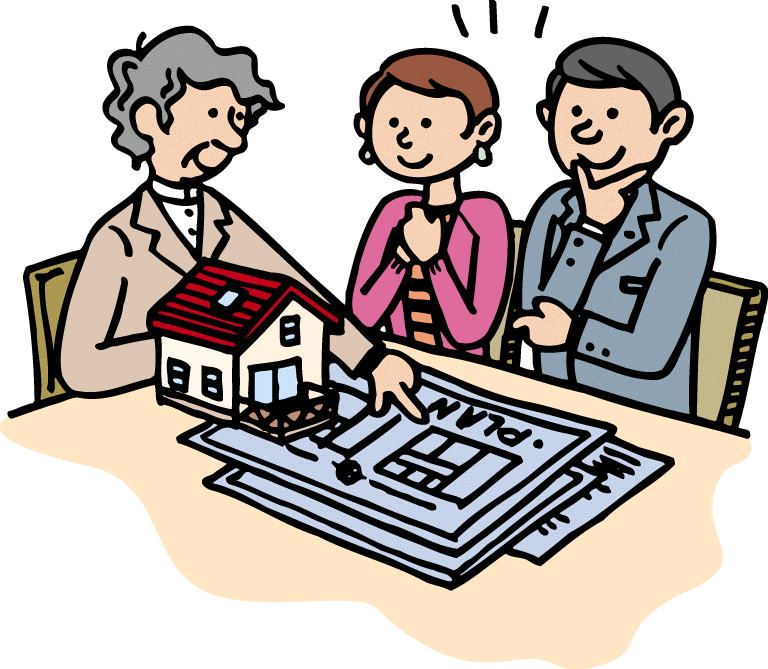
建築条件付き土地売買契約のケースなどでは、土地の売買契約締結後、直ちに建物の建築請負契約を締結するケースがあります。この段階では、何も「家の内容」が決まっていなくても、請負契約書に印鑑を押してしまいがちです。
口頭だけでも請負契約が成立するのですから、間違いなくこのような状況では請負契約は成立します。
例え、「何も決まってなくとも」
大事なのは、図面や仕様書を作成し、「どのような家」を建てるのか?
その図面や仕様書を基に、見積書を作成し建築費用がいくらかかるのか?工事金額を明らかにしたうえで、注文者・施工者であるあなたと施工業者が「請負契約」を成立させることが重要です。
請負契約の締結を急がれたら要注意
請負契約の目的となる、具体的な「建築物」つまり家の内容が決まっていない段階で、「とにかく契約だけ」と言って請負契約を急がせる場合は要注意だと感じています。
施主・注文者は請負契約の締結を急ぐ理由・急ぐ感じを持っていないケースが殆どであると思います。
じっくりと納得いくまで建物の打合せをし、検討し、どのような家を建てるのか、しっかりと理解した上で請負契約を締結したいと言うのが一般的な思いでしょうが、多くの人が初めての経験であるので、ここでは一般論は施工業者等に言われる内容に終始するの場合がほとんどです。
具体的にどのような家を建築するかまとまってきた段階では、いくつもの図面や仕様書が作成されてくることが少なくないのが一般的です。もちろんこれらを作成するためには多大な労力がかかるので、この時点で少しでも早く請負契約を先行させたいのは、施工業者等の立場で考えれば、確かにそうであろう。
しかし、いくつものプランを検討し、内容を精査して家づくりするのが普通だろうと考えます。家を作る立場からはプラン等が確定した段階で初めて請負契約の締結準備ができるのも事実でしょう。
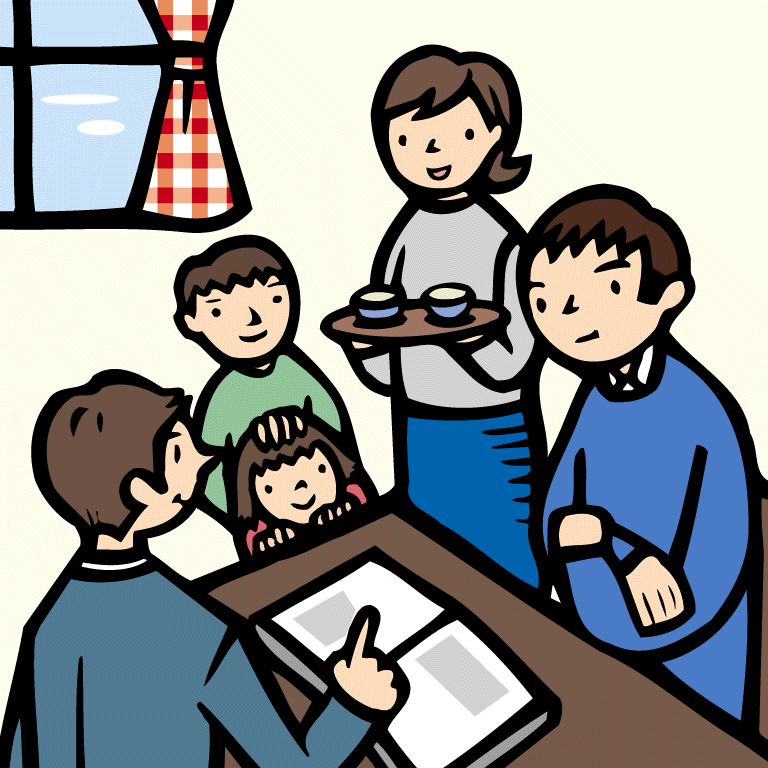
問題は、施主・建築主のタイミングか?施工業者のタイミングか?
どのタイミングで請負契約をするのがトラブルを無くすのでしょうか?
やはり、施主・建築主にとってのタイミングを優先した請負契約の方が建築上のトラブルは少ないと考えます。
そして、このタイミングを見極めるためのポイントは、「設計図書と仕様書」の出来だと考えます。
一般の施主や建築主はこれらの資料ができても、「図面なんて見てもわからない」と言われる方もいます。
そう言った時には、セカンドオピニオンとして他の建築士等に客観的な意見を聞いてみるのも、理解を深めるのも方法です。
更に、請負契約締結時に注意していただきたいのは、膨大な検討を繰り返してきた図面や仕様書の数量が非常に多くあるため、最終的にどの案に決定したのかをはっきりさせておくことはとても重要です。
請負契約を締結する際には、最終決定した図面・仕様書・見積もりを三点セットとして請負契約書に添付して契約する、あるいは請負契約との関連を明示した上で請負契約を締結するといった方法が防御策として有効だと考えます。
これらの図面・仕様書・見積もり内容を請負契約書に関連付けていない場合は、しっかりと関連付けるように業者に変更を要望しましょう。
「何となく、流されて・・・」という行為は、後でのトラブルを招く恐れがあります。こういった作業・確認の積み重ねが、後々の紛争の際に大事であることは、ここまで読んで頂ければ理解できると思います。
建築トラブルを起こさないために・・・一歩ずつ進めていくことが大事だと思います。
施主・注文者は請負契約の締結を急ぐ理由・急ぐ感じを持っていないケースが殆どであると思います。
じっくりと納得いくまで建物の打合せをし、検討し、どのような家を建てるのか、しっかりと理解した上で請負契約を締結したいと言うのが一般的な思いでしょうが、多くの人が初めての経験であるので、ここでは一般論は施工業者等に言われる内容に終始するの場合がほとんどです。
具体的にどのような家を建築するかまとまってきた段階では、いくつもの図面や仕様書が作成されてくることが少なくないのが一般的です。もちろんこれらを作成するためには多大な労力がかかるので、この時点で少しでも早く請負契約を先行させたいのは、施工業者等の立場で考えれば、確かにそうであろう。
しかし、いくつものプランを検討し、内容を精査して家づくりするのが普通だろうと考えます。家を作る立場からはプラン等が確定した段階で初めて請負契約の締結準備ができるのも事実でしょう。
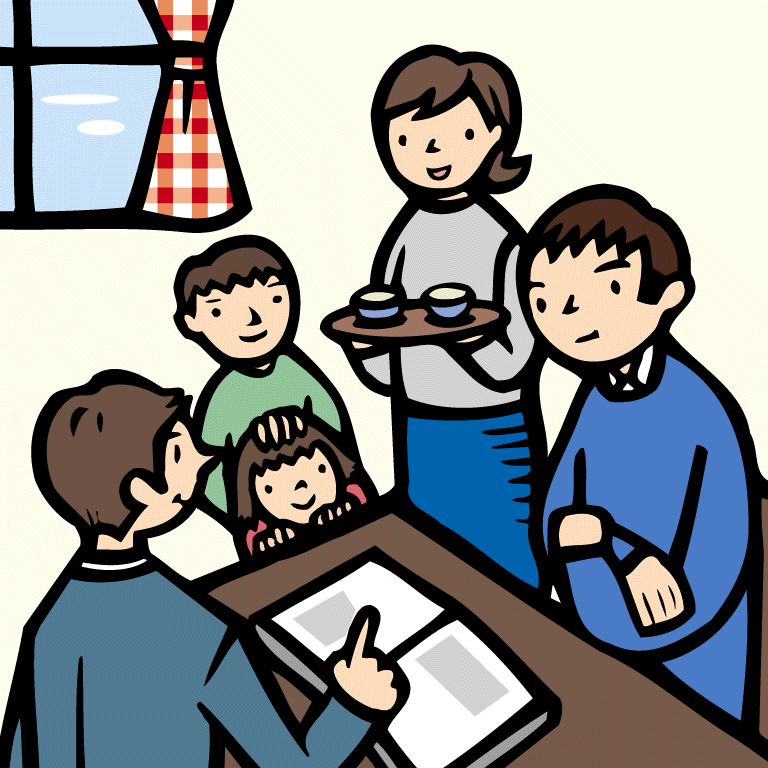
問題は、施主・建築主のタイミングか?施工業者のタイミングか?
どのタイミングで請負契約をするのがトラブルを無くすのでしょうか?
やはり、施主・建築主にとってのタイミングを優先した請負契約の方が建築上のトラブルは少ないと考えます。
そして、このタイミングを見極めるためのポイントは、「設計図書と仕様書」の出来だと考えます。
一般の施主や建築主はこれらの資料ができても、「図面なんて見てもわからない」と言われる方もいます。
そう言った時には、セカンドオピニオンとして他の建築士等に客観的な意見を聞いてみるのも、理解を深めるのも方法です。
更に、請負契約締結時に注意していただきたいのは、膨大な検討を繰り返してきた図面や仕様書の数量が非常に多くあるため、最終的にどの案に決定したのかをはっきりさせておくことはとても重要です。
請負契約を締結する際には、最終決定した図面・仕様書・見積もりを三点セットとして請負契約書に添付して契約する、あるいは請負契約との関連を明示した上で請負契約を締結するといった方法が防御策として有効だと考えます。
これらの図面・仕様書・見積もり内容を請負契約書に関連付けていない場合は、しっかりと関連付けるように業者に変更を要望しましょう。
「何となく、流されて・・・」という行為は、後でのトラブルを招く恐れがあります。こういった作業・確認の積み重ねが、後々の紛争の際に大事であることは、ここまで読んで頂ければ理解できると思います。
建築トラブルを起こさないために・・・一歩ずつ進めていくことが大事だと思います。
建築トラブル・住宅トラブルを避けるために!
請負契約は金額的にも高額であり、不動産購入時と同等の覚悟・判断が求められるものだと思うが、その請負契約締結のプロセスにおいては、「消費者保護」と言った観点はあまり考慮されているとは思えないのが現状です。
不動産の契約においては、重要事項の説明や契約内容の説明が不動産業者には課せられているが、請負契約にはそのようなプロセスはありません。
ついつい、簡単に契約を締結しがちですが、そのあとのトラブルは簡単に解決できないのが現実です。
請負契約締結前に、これだけのポイントがあります。
建築トラブル・住宅トラブルを回避するための方法として、請負契約の契約締結まえにじっくり考えてみてください。
住宅建築の際のセカンドオピニオンを実施しています。
不動産の契約においては、重要事項の説明や契約内容の説明が不動産業者には課せられているが、請負契約にはそのようなプロセスはありません。
ついつい、簡単に契約を締結しがちですが、そのあとのトラブルは簡単に解決できないのが現実です。
請負契約締結前に、これだけのポイントがあります。
建築トラブル・住宅トラブルを回避するための方法として、請負契約の契約締結まえにじっくり考えてみてください。
住宅建築の際のセカンドオピニオンを実施しています。
バナースペース
| お知らせ:TOP‐NEWS |
相談は1回5,000円・現地への出張は、1回20,000円(神奈川県内) 納得いかない場合は完全返金! |
横浜住宅建築相談所
〒231-0012
横浜市中区相生町1-3
モアグランド関内ビル5階
TEL 0120-375-530(相談予約専用)
TEL 045-650-2103
FAX 045-650-2104
Mail info@trustship.co.jp
Tweet